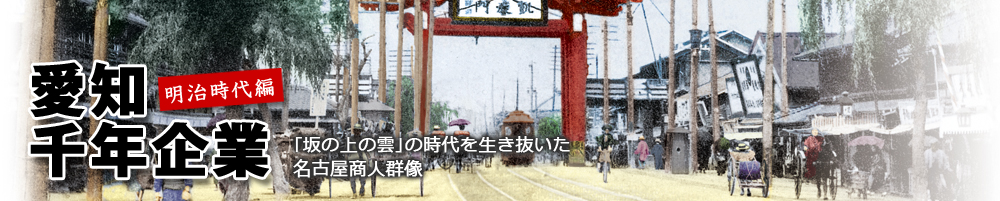
- トップ
- 明治時代編トップ
- 第1部 西南戦争起こる
- 本町のシンボル・長谷川時計を作る
第1部 明治前期/1877(明治10年)

本町のシンボル・長谷川時計を作る

玉屋町の長谷川時計塔
『歴史写真集 名古屋再発見』(中日新聞本社)より
前述したが、明治時代の名古屋の町名には「玉屋町」という所があった。本町の南側で、三菱東京UFJ銀行の場所といえばすぐ分かることだろう。
この玉屋町は、江戸時代には、桔梗屋呉服店や、本居宣長の「古事記伝」出版で有名な永楽屋東四郎こと永東書店もあり、大きな商人が軒を連ねていた。居酒屋が軒を並べ、遊女を置く店もあった。

明治時代は、三菱東京UFJ銀行の場所を玉屋町といった
(●は当時の場所)
この玉屋町に、明治10年(1877)、長谷川時計塔ができた。デンとそびえる時計塔の偉容は、当時の玉屋町の景観を一変させた。異彩を放ち、街のシンボルになった。時計が奏でる音は、チーンと固く、梵鐘のように余韻があり、しかも瞬間よく響き渡り、歯切れが良かった。〔参考文献『明治・名古屋の顔』(服部鉦太郎 六法出版社)〕
愛知県織工場を設立 名古屋の織物業の始まり
名古屋の織物業は、明治10年(1877)に久屋町で設立された学校兼工場・愛知県織工場に始まる。この工場の設立目的は、士族の婦女子への機織り技術の伝習と、輸入超過を食い止めるための国産化であった。
工場は県営だったが、尾張徳川家としても経済的に支援することになり、毎年多額の援助を行った。
この工場への入社を希望する者は、旧藩士の窮乏が進むとともに急増した。そこで明治12年には筒井町(後の堅代官町)に分工場を開設した。さらに同年に分工場が名古屋区下堀川町(現・名古屋市中区堀川町)でもできた。明治13年には愛知郡上名古屋村(現・名古屋市)でも造られた。
この工場での織物技術の伝習の実態は、明治16年の「織工場規則」で垣間見ることができる。生徒は12歳以上の女子であり、生徒はその技術レベルによって4等級に区分され、その等級によって日当金・織賃あるいは月料が支払われた。
この工場で技術を習得した卒業生は、そのままその工場で働くか、愛知物産組などの織物工場に入って働いた。〔参考文献『新修名古屋市史』〕
名古屋に初の銀行を設立
政府は明治5年(1872)、国立銀行条例を公布し、新たな金融制度の創出に乗り出した。伊藤博文は発券銀行制度を導入しているアメリカ合衆国のナショナル・バンク制度を参考に建議し、国立銀行条例を明治5年に公布した。なお、国立銀行といっても、「国法によって立てられた銀行」という意味であり、実際には民間銀行だった。
この政策に沿った形で名古屋でも銀行が設立された。第十一国立銀行がそれで、明治10年に、名古屋区長吉田禄在の呼びかけで、尾張藩御用達商人であった「いとう呉服店」(現・大丸松坂屋百貨店)の伊藤次郎左衞門らによって茶屋町(現・中区丸の内2‐5。アイリス愛知)に設立された。資本金は10万円。初代頭取は、伊藤次郎左衛門が就任したが、その後は吹原九郎三郎、岡田良右衛門、関戸守彦へと交代した。発足時の場所は、伊藤次郎左衛門の近くの茶屋町3‐7(現・中区丸の内2丁目)だったが、その後で上長者町4丁目15に移転した。
また、尾張藩の旧士族が中心になって設立した銀行もあった。第百三十四国立銀行がそれで、明治11年に設立された。尾張藩元家老志水忠平らが、旧尾張藩士族の金禄公債などを資本に名古屋に設立した。資本金は15万円。初代頭取には岡谷惣助が就任。場所は和泉町2丁目7(現・中区丸の内1丁目)だった。
この第十一国立銀行と第百三十四国立銀行は後に合併し、愛知銀行(東海銀行の前身の一つ)に統合され、歴史の幕を閉じた。
それから隣接県の岐阜・三重でも同様の動きがあった。岐阜では、十六銀行が明治10年に設立された。
大垣では、大垣共立銀行の前身である第百二十九国立銀行が明治11年に創立された。名称は、株主に旧大垣藩士族と西濃各郡の地主が加わったことから、士族と平民が協力して新発足したので、「共立」にした。
三重では、明治11年に旧津藩(藤堂氏)の武士たちにより、第百五国立銀行が設立された。明治30年には、普通銀行に改組、株式会社百五銀行となった。
序文
第1部 明治前期
明治元年 龍馬暗殺
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 伊藤祐昌(いとう呉服店)
- この年に創業 峰澤鋼機
明治2年 版籍奉還
明治3年 四民平等
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 九代目岡谷惣助真倖(岡谷鋼機)
明治4年 通貨単位が両から円へ
- その時、名古屋商人は・・・
- 岡谷鋼機が会社を作って七宝焼を世界に売り込む
明治5年 新橋―横浜間に鉄道開通
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 北川組
- この年に創業 鯛めし楼
明治6年 地租改正
明治7年 秋山好古が風呂焚きに
明治8年 北海道に屯田兵を置く
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 四代目滝兵右衛門(タキヒヨー)
- この年に創業 タナカふとんサービス
- この年に創業 青雲クラウン
明治9年 武士が失業へ
明治10年 西南戦争起こる
- その時、名古屋商人は・・・
- 本町のシンボル・長谷川時計を作る
- この年に創業 一柳葬具總本店
明治11年 大久保利通暗殺
明治12年 コレラが大流行
明治13年 官営工場が民間へ払下げ
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 安藤七宝店
明治14年 緊縮財政始まる
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 岩間造園
- この年に創業 松本義肢製作所
- この年に創業 東郷製作所
明治15年 板垣退助暴漢に襲われる
明治16年 欧化を推進、鹿鳴館外交始まる
明治17年 自由民権活動が激化
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 村上化学
明治18年 伊藤博文、初代首相に
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 福谷
- この年に創業 服部工業
明治19年 ノルマントン号事件起きる
明治20年 豊田佐吉、発明家として歩み出す
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 林市兵衛
- この年に創業 折兼
- この年に創業 鶴弥
- この年に創業 柴山コンサルタント
明治21年 正岡子規、ベースボールに夢中
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 鈴木政吉
- この年に創業 ニイミ産業
- この年に創業 丸川製菓
明治22年 大日本帝国憲法発布
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 坂角総本舗
明治23年 教育勅語発布
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 ヒノキブン
- この年に創業 笹徳印刷
- この年に創業 ワシノ機械
明治24年 ロシア皇太子、斬られる
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 河田フェザー
明治25年 第二回総選挙で、政府が選挙妨害
明治26年 御木本幸吉、真珠養殖に成功
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 奥田正香
- この年に創業 西脇蒲團店
第2部 日清・日露戦争時代
第3部 明治後期
第4部 「旧町名」を語りながら
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274