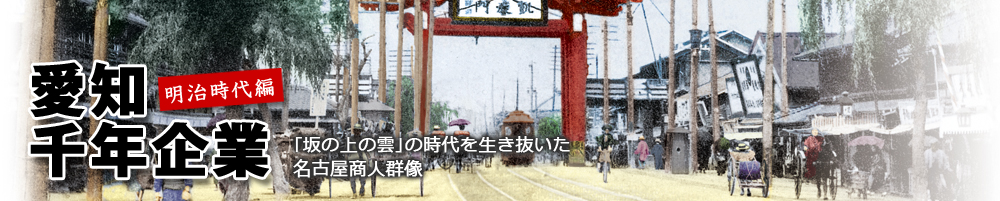
第1部 明治前期/1869(明治2年)
版籍奉還。
名古屋商人には3つのルーツがある
版籍奉還という名の徳政令
版籍奉還は、後の廃藩置県につながる大きな改革であった。諸大名が領地(版図)と領民(戸籍)を天皇家に奉還するというものだった。これにより新政府は、全国に命令を出せるようになり、ようやく統一国家としての形が整った。
版籍奉還において、藩主は藩の収入の一部を保障されたうえで、華族に列せられた。公卿、大名らの称を廃し、華族と改めた。
大名は、それまでに残した借財に関して、責任を問われることもなかった。だから、お殿様たちにしてみれば、いってみれば借金棒引きの徳政令であり、反対する理由などなかった。
わが尾張藩は、明治2年(1869)2月に版籍奉還を申し出ている。
名古屋商人の3つのルーツ
ここで名古屋商人と呼ばれた人たちのルーツを解説しよう。名古屋は、御三家筆頭の尾張藩の城下町として、豊かな地域だった。その財力と系譜は、明治以降にも引き継がれていった。
名古屋の商人は、その出身の違いから主に3つに区分される。
第1グループは、土着派である。これは「清須越」を中心とする尾張徳川家の御用達商人の系譜だ。前述した通り、尾張藩は商人を格付けしていた。
現代につながるところでいえば、伊藤次郎左衛門(後の松坂屋)、笹屋の岡谷惣助(後の岡谷鋼機)、十一屋の小出庄兵衛(後の丸栄)、知多屋の青木新四郎(後の名エン)、材木屋の鈴木惣兵衛(後の材惣木材)などである。
第2グループは、近在派である。その代表的存在は、滝兵右衛門(現・タキヒヨー)、瀧定助だ。尾張藩の御用達商人とは異なり、彼ら自身の才覚により、台頭してきた。近藤友右衛門(信友)、八木平兵衛、原田勘七郎らもこの系譜に属する。
第3グループは、外様派である。これは主に県外出身者であった。その代表は豊田佐吉だった。いうまでもなく佐吉は湖西の出身である。また、オークマを創業した大隈栄一も外様派の1人だった。それから森村グループの創業者である森村市左衛門も他国派の1人といえそうだ。
これらのグループは、常に競い合うような形で起業することが多かった。例えば銀行とか、紡績業とか、倉庫業とか、何かしら競い合っていた。
やる気の源泉はお金と飯 明治時代の商家の労務管理
明治時代の商家の店員は、当時6年制だった尋常小学校か、あるいはさらに2年間勉強する高等科のいずれかを卒業して、丁稚として入店した。名古屋市外の郡部出身者は前者、名古屋市内在住者は後者が多かった。いずれにしても、12歳か14歳だった。
丁稚時代は「何吉」という呼称を与えられた。幼い丁稚は、まず奥の仕事から修業した。掃除、水汲み、薪割り、風呂焚きなどだった。そういう中で、行儀や挨拶をしつけられた。
この修業を済ませて10代半ばになると、外回りに出掛けることになった。初めは先輩が同行したが、しばらくして単独になる。計算や記帳の誤り、連絡ミス、帰店時刻の遅刻などは厳しく注意された。時にはソロバンで頭を殴られることもあった。
丁稚小僧の時代は、木綿ガスリの着物を着用した。基本的に素足で、冬でも着用を許されなかった。だが18歳になると、元服して羽織と煙草入れをもらうのが通例だった。足袋も履かせてもらえた。
明治30年代の丁稚小僧は、お小遣いとして、盆・暮れなど特別な行事の都度、それぞれの経験と年齢に応じて、1円から2円をもらった。年間では、10円から15円ほどだったが、衣食住付きだったから、生活には困らなかった。
丁稚が商いの駆け引きを身に付け始める頃になると、やがて徴兵検査の年がやってきた。徴兵検査は満20歳になったら行われた。
この徴兵検査が済むと、もう一人前となった。丁稚としての修業が終わると、次は手代になった。手代になったら呼称が「何七」という風に変わった。手代になると、初めて羽織を着ることが許された。決算祝いの際には、店の幹部や来賓と席を同じくして「何七」という改名披露も行われた。
「見習店員○吉ヲ通常店員トナシ、○七ト改名ス」
墨でくろぐろと書かれた自分の改名披露を誇らしげに見上げ、新しい羽織の袖を引っ張ってみるのが丁稚の見習い店員の目標だった。
商家の勤務時間は、季節によって異なっていた。4月から9月までの間は、午前5時起床で、6時出勤、午後10時就寝だった。10月から3月までの間は、午前6時起床、7時出勤、午後11時就寝だった。
住み込み時代の息抜きは、たまの外出だった。外出は毎月1回認められていて、門限が7時と決められていた。その外出時においても、外食は禁じられていた。
実家に戻ることは年1回許されていた。おおむね1週間程度で、旅費、小遣い、土産代まで支給された。
それから今でいうところの社員旅行もあった。店の閑散期には、例えば3泊4日で旅行に行った。名古屋の商家の場合、例えば蒲郡の海岸など、山や海へ出掛けた。
給与は、丁稚時代に10等級、手代時代に13等級ぐらいに分けられていた。おおむね半年に1等級ずつ昇給することが多かった。今日の年功給与の原型がそこにあった。
今でいうところの〝大入り〟のようなことも行われていた。月商が目標を超えた際には、その労をねぎらう意味で、ご馳走が振る舞われた。例えば、鶏肉とか、すき焼きだった。食べ盛りの店員たちだから、この大盤振る舞いが一番の楽しみだった。だから毎月末になると「それ、もう少しですき焼きだ」「見落としはないか、もう一度よく調べろ」という掛け声が聞かれた。
給与のほかに賞与も支給されていた。決算期が無事終わり、良い結果が出た時は店員に分配された。これが大いに励みになった。だから店側も「一生懸命に働けば、その報酬は必ずあるものだ。だが、それには順序がある。まず木の幹を太らせ(店を繁盛させ)、そこから枝葉を伸ばせ(各人の報酬)」と店員に叩き込んでいた。
今でいうところの〝退職金〟のような制度もあった。給与の一部は、主人が積み立てていて、将来別家する時にまとめて支給されたのだ。お互いの信頼関係を基礎にした賃金後払い制だった。
10年以上住み込み店員を続けて、年も20代半ばになると、別家を許された。それまでの住み込みから解放されて独立するのである。その際には、家具・什器・布団・鍋・釜・米・味噌・塩・醤油まで支給されたので、一切合切に至るまで面倒をみた。そのうえで、積立金と祝い金まで付いていた。住居は、主人の借家を使うことが多かった。家賃は通常の半額を会社が負担することが多かった。
この20代半ばというのは、男の適齢期でもあった。親たちは息子の結婚の相談を主人にお願いしにくるようになり、主人も面倒見良く世話を焼いたものだった。
別家といっても、そのまま勤務を続ける「仮別家」と、暖簾分けということで独立自営をする「本別家」があった。仮別家とは、妻帯して通勤するようになることだった。そうなると〝本当の一人前の店員〟とみなされた。給与は月給になった。
仮別家を許された番頭は、さらに1年間の「お礼奉公」をするのが、義務付けられた習慣だった。それが済むと、去就は自由となり、独立するのも、転職するのも自由だった。
本別家となって独立する者に対しては、仕入れ帳が渡された。この仕入れ帳は価値があった。というのは、仕入れ先から信用取引で商品を購入できたからだ。当時はもの不足だったので、商品さえ入れば商売は成功したのと同じだった。
このように明治時代の雇用関係は、江戸時代からのものの考え方や習慣を引き継いだものだった。ひとたび雇用関係に入ったからには、主人は使用人の生活の面倒をみていくものだった。使用人の側にも、主人のために身を粉にして働くものだということが当然だと考えていた。〔参考文献『森林の歩み』、『瀧定百三十年史』、『人 八神製作所一一一年史』〕
序文
第1部 明治前期
明治元年 龍馬暗殺
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 伊藤祐昌(いとう呉服店)
- この年に創業 峰澤鋼機
明治2年 版籍奉還
明治3年 四民平等
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 九代目岡谷惣助真倖(岡谷鋼機)
明治4年 通貨単位が両から円へ
- その時、名古屋商人は・・・
- 岡谷鋼機が会社を作って七宝焼を世界に売り込む
明治5年 新橋―横浜間に鉄道開通
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 北川組
- この年に創業 鯛めし楼
明治6年 地租改正
明治7年 秋山好古が風呂焚きに
明治8年 北海道に屯田兵を置く
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 四代目滝兵右衛門(タキヒヨー)
- この年に創業 タナカふとんサービス
- この年に創業 青雲クラウン
明治9年 武士が失業へ
明治10年 西南戦争起こる
- その時、名古屋商人は・・・
- 本町のシンボル・長谷川時計を作る
- この年に創業 一柳葬具總本店
明治11年 大久保利通暗殺
明治12年 コレラが大流行
明治13年 官営工場が民間へ払下げ
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 安藤七宝店
明治14年 緊縮財政始まる
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 岩間造園
- この年に創業 松本義肢製作所
- この年に創業 東郷製作所
明治15年 板垣退助暴漢に襲われる
明治16年 欧化を推進、鹿鳴館外交始まる
明治17年 自由民権活動が激化
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 村上化学
明治18年 伊藤博文、初代首相に
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 福谷
- この年に創業 服部工業
明治19年 ノルマントン号事件起きる
明治20年 豊田佐吉、発明家として歩み出す
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 林市兵衛
- この年に創業 折兼
- この年に創業 鶴弥
- この年に創業 柴山コンサルタント
明治21年 正岡子規、ベースボールに夢中
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 鈴木政吉
- この年に創業 ニイミ産業
- この年に創業 丸川製菓
明治22年 大日本帝国憲法発布
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 坂角総本舗
明治23年 教育勅語発布
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 ヒノキブン
- この年に創業 笹徳印刷
- この年に創業 ワシノ機械
明治24年 ロシア皇太子、斬られる
- その時、名古屋商人は・・・
- この年に創業 河田フェザー
明治25年 第二回総選挙で、政府が選挙妨害
明治26年 御木本幸吉、真珠養殖に成功
- その時、名古屋商人は・・・
- 明治名古屋を彩る どえりゃー商人 奥田正香
- この年に創業 西脇蒲團店
第2部 日清・日露戦争時代
第3部 明治後期
第4部 「旧町名」を語りながら
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274