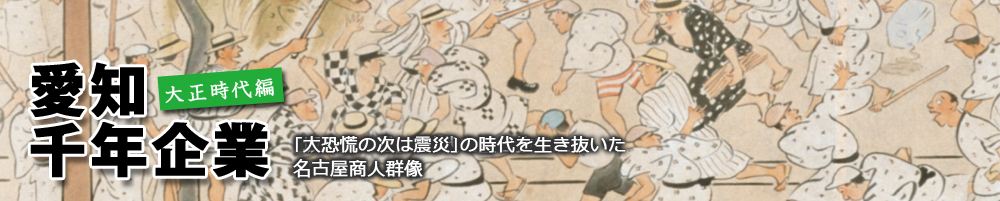
大正12年(1923)9月1日に関東大地震が発生。死者10万人
その頃、世界は…ドイツが超インフレ
日本が震災後の混乱で苦しんでいる最中、敗戦国のドイツも苦しんでいた。ドイツは、ベルサイユ条約で莫大な賠償金を課されていたが、経済的疲弊から支払いが滞っていた。そこでフランス・ベルギー軍がルール工業地帯を占領した。
ドイツは、戦後の超インフレに悩まされていた。インフレは、賠償の不履行を口実にフランスがルール工業地帯を占領すると頂点に達した。1月に250マルクだったパンの価格は7月には2千億マルクに急騰した。
この混乱の中で国民の不満は一挙に噴出し、アドルフ・ヒトラーの台頭を招くことになる。
その頃、名古屋は…初めて家計調査が行われる
この大正12年(1923)は、家計調査が名古屋で最初に行われた年だった。名古屋市は、市内にある工場を選定し、家計簿を配付し、常傭労働者(402世帯)の生計費調査を開始した。総収入平均は月額95円だった。業種ごとにランキング表(低い順)を作ると、次のようになっている。
①窯業(陶器職工)81円、②紡織(紡績職工、職工)81円、③公営事業(市電従業員)84円、④電気ガス(ガス工)86円、⑤官業(専売局職工)93円、⑥学芸趣味(楽器工)95円、⑦船舶車両(自転車工、車両工)96円、⑧機械器具(内撚機械・ポンプ工・機械工・鉄工)112円
ちなみに、名古屋市長の年俸は1万円(月額833円)だった。
この年に誕生した人…敗戦体験が作家生活の原点に 司馬遼太郎
司馬遼太郎は、大正12年(1923)、大阪市で薬局を経営する父福田是定(薬剤師)、母直枝の次男として生まれた。
昭和18年(1943)に、学徒出陣により大阪外国語学校(大阪大学外国語学部の前身)を仮卒業。戦車隊に入隊した。昭和19年、満州の戦車学校に入校し、12月に卒業。卒業後、満州に展開していた隊に小隊長として配属される。
昭和20年に、本土決戦のため栃木県佐野市に移り、ここで陸軍少尉として終戦を迎えた。この敗戦の体験が、その後の作家生活の原点になった。
司馬は、「なぜこんな馬鹿な戦争をする国に産まれたのだろう? いつから日本人はこんな馬鹿になったのだろう?」との疑問をもち、「昔の日本人はもっとましだったにちがいない」として、「22歳の自分へ手紙を書き送るようにして小説を書いた」と述懐している。
発刊に寄せて
序文
大正元年(1912)
大正2年(1913)
大正3年(1914)
大正4年(1915)
大正5年(1916)
大正6年(1917)
大正7年(1918)
大正8年(1919)
大正9年(1920)
大正10年(1921)
大正11年(1922)
大正12年(1923)
9月1日に関東大地震が発生。死者10万人
- その頃、日本は 震災が経済に大打撃
- その頃、名古屋は 銀行が取り付け騒ぎに遭う
- その頃、名古屋は 大震災直後に大売り出しを挙行した、いとう呉服店
- その頃、豊田は 佐吉が刈谷で織機試験工場を新設
- その頃、名古屋は 遊郭が大須から大門に移転
- その頃、世界は ドイツが超インフレ
- <この年に誕生した会社>
“地味で堅実”を地でいく管工機材の商社 大清 - <この年に誕生した会社>
「リスクを恐れるな」三兄弟の挑戦により発展 シロキ - <この年に誕生した会社>
薬局から始まり医療・福祉の総合企業へ ナンブ - <この年に誕生した会社>
材木商として港と共に生きる
名古屋港木材倉庫 - <この年に誕生した会社>
学校給食の分野で実績 天狗缶詰
大正13年(1924)
大正14年(1925)
大正15年(1926)
昭和2年(1927)
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274