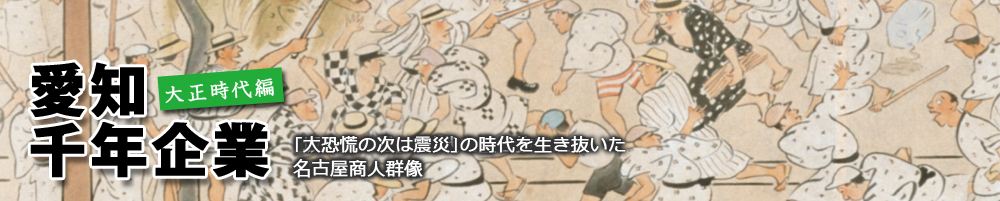
大正5年(1916)
吉野作造が名古屋で民本主義を説く
政治学者の吉野作造は、大正5年(1916)から、大正デモクラシーを代表する思想として民本主義を唱え始めた。民主主義と民本主義はよく似た言葉だが、吉野があえて「民主主義」と言わなかったのは大日本帝国憲法が天皇主権制をとっていたためだ
だが、吉野を批判する勢力も強かった。憲法学者の上杉慎吉は、吉野の民本主義を激しく批判した。
吉野が初めて名古屋の聴衆にまみえたのは、大正7年だった。同年1月と12月に行われた2回の講演には、1千人にのぼる聴衆が集まった。吉野は、8年にも来名して「普選に伴う諸問題」と題して講演した。普通選挙を求める人々が集まり、会場は異様な興奮に包まれた。
その頃、日本は…好景気で狂乱物価
大正5年(1916)に入ると、ヨーロッパでの戦乱が拡大し、重化学工業製品を中心としてアジア市場に向けたヨーロッパ製品の輸出の急減とヨーロッパからの需要が急増した。このため、アジア市場・アメリカ市場を中心に日本品の輸出がこの年から増大し、6月以降急増した。
こうして日本は、ヨーロッパの人々の苦しみをよそに、莫大な利益をあげた。日本が近代工業国としての発達に必要な元本としての資本を蓄積し得たのは、すべて第一次世界大戦時における巨額の企業利潤が基になった。
狂乱物価は、名古屋でも同じだった。輸出の急増とヨーロッパ製品の輸入の急減・杜絶は、国内の品不足を招き、工業製品の値段を急騰させた。品不足による工業製品の価格急騰は、生産拡大を促進させ、労働力需要を急増させた。
輸出は活況を呈し、国内は鉄鋼をはじめ重工業が勃興し、あらゆる産業が活況を呈した。なかでも鉄鋼・非鉄金属部門は、「つくれば何でも売れる」という状況であった。寛文9年(1669)名古屋にて創業の鉄鋼商社岡谷鋼機の社史には、こんなデータも載っている。
「鉄価格相場は、大正4年10月に丸鋼(1トン)が136円だったが、大正6年10月になると378円になった」
大戦による異常な企業勃興は、労働者の争奪につながった。労働需要の激増は賃金の上昇をもたらした。
〔参考文献『大正昭和財界変動史 上巻』〕
その頃、日本は…ドイツの休戦の申し入れで株価が暴落
東京の株式市場が、戦争景気らしい騰勢を示し始めたのは、大正4年(1915)11月下旬からであり、すなわち、第一次世界大戦開戦後約16カ月を経てからであった。しかし、その後においても騰勢は一進一退を繰り返し、沸騰人気らしい投機熱を示したのは、ようやく大正5年11月および12月になってからであった。
名古屋株式取引所では、大正5年の前半、和平説なども出て前年高騰の反動安となったが、後半は日露新協約の成立、各事業会社の増資増配等から市場は未曽有の活況となり、11月、名株の株価は266円の新高値を記録した。
だが、そこに急報が入った。12月12日、ドイツはウィルソン米大統領を通じて、連合国側に休戦を申し入れた。13日、ドイツ講和提議の報を受けて、東京株式市場が大暴落した。18日まで停会。だが30日、連合国側はこれを拒絶した。
しかしドイツ講和提議の報に、諸株一斉に暴落して収拾のつかぬ惨状を呈し、名株は13日から売買立会を停止し、18日および22日に立会を挙行したのみで臨時休会のまま越年した。同年の名株売買高は、460万株と記録を更新した。
〔参考文献『名古屋証券取引所三十年史』〕
次のページ その頃、名古屋は…大戦のおかげで重工業が勃興
発刊に寄せて
序文
大正元年(1912)
大正2年(1913)
大正3年(1914)
大正4年(1915)
大正5年(1916)
吉野作造が名古屋で民本主義を説く
- その頃、日本は 好景気で狂乱物価
- その頃、名古屋は 大戦のおかげで重工業が勃興
- その頃、日本は 工場法が施行され不十分ながら労働者保護へ
- <この年に誕生した会社>
ピンチを一致団結して乗り切る
クサカ - <この年に誕生した会社>
「もったない」精神をビジネスに エス・エヌ・テー - <この年に誕生した会社>
ロングセラーの「あべっ子ラムネ」 安部製菓 - <この年に誕生した会社>
「土木は世の中を良くする仕事」の信念を貫く 朝日工業 - <この年に誕生した会社>
自己変革に挑む地場の繊維産業
茶久染色 - <この年に誕生した会社>
「長生き健康法」で企業を永続
妙香園
大正6年(1917)
大正7年(1918)
大正8年(1919)
大正9年(1920)
大正10年(1921)
大正11年(1922)
大正12年(1923)
大正13年(1924)
大正14年(1925)
大正15年(1926)
昭和2年(1927)
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274