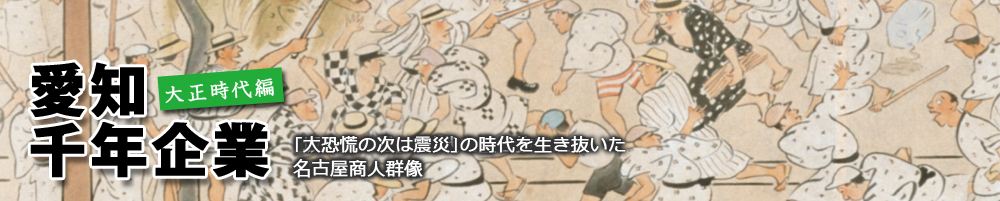
大正5年(1916)吉野作造が名古屋で民本主義を説く
その頃、名古屋は…大戦のおかげで重工業が勃興
第一次世界大戦は、名古屋の重工業の勃興期のきっかけとなった。
明治期の織物・ポンプ・揚水機・麺機などや、鉄道車両や自転車生産が緒に就いた名古屋の機械器具工業は、大戦期に飛躍的に発展するとともに、それらを土台に工業用諸作業機・電気器械器具・工作機械の生産を発展させ、航空機生産も開始された。また、これら機械器具生産に材料を供給する金属工業もこの時期に勃興した。
機械器具工業をこの期にリードしたのは、織機と鉄道車両だった。織機生産の発展は、言うまでもなく大戦期の紡績業の飛躍的発展にあった。この好機に名古屋に繊維メーカーが次々と設立された。
名古屋の車両製造のうち、圧倒的生産額を占める鉄道・電鉄関係車両は、大阪の汽車製造、神戸の川崎車輌と並び日本3大車両と呼ばれた日本車輌製造がもっぱら担っていた。
第一次世界大戦後、名古屋の貿易構造には大きな変化が生じることになる。名古屋港は第一次世界大戦末期に取扱額を急増させ、戦後もそれを持続しただけでなく、加速させた。名古屋港の取扱額は大正5年(1916)の1千300万円から7年には3千400万円、9年には5千600万円へと急増し、5大港の仲間入りをした名古屋港は、11年を画期に輸出入が逆転し、昭和8年(1933)まで恒常的な入超構造に転換した。この急速な転換をもたらした商品が、木材、綿花、羊毛であった。〔参考文献『新修名古屋市史』〕
その頃、名古屋は…大同特殊鋼のルーツが創業
福澤桃介は、八百津発電所が運転を開始した頃、余剰電力の消化に悩んでいた。そこで電気の消化をする事業に挑戦することになった。電鉄事業にも手をのばし、大正3年(1914)の8月に名古屋鉄道の前身たる愛知電気鉄道の社長におさまった。
桃介はそれに加えて、電気製鋼も開始することにした。名古屋電燈では大正3年に電気製鋼の計画が持ち上がり、4年10月に同社内に製鋼部が設置され、熱田東町にて第1期建設工事を開始した。5年8月には、名古屋電燈から分離する形で、資本金50万円で株式会社電気製鋼所を設立した。我が国最初の電気製鋼所の設立であった。桃介は、そこで翌6年11月に社長になった。
また、大正7年9月に名古屋電燈の製鉄部から独立して設立された木曽電気製鉄(翌年10月木曽電気興業と改称)があり、そこは10年2月に大同電力株式会社が設立されると、同社の名古屋製鉄所となった。
この名古屋製鉄所が同年11月に分離独立して大同製鋼株式会社となり、翌11年7月には5年に設立された株式会社電気製鋼所を合併して、株式会社大同電気製鋼所となった。大同電気では各種合金鉄・鍛鋼品・圧延鋼・スプリング・鋳鋼品などを生産した。
この大同電気製鋼所が大同特殊鋼の始まりである。〔参考「大同特殊鋼ホームページ」〈http://www.daido.co.jp〉〕
その頃、名古屋は…大隈麺機商会が大隈鐵工所に改称
工作機械のオークマは、製麺機メーカーの大隈麺機商会がルーツだった。大隈麺機商会は、その名のとおりうどんの機械をつくる業務で明治時代に創業した。
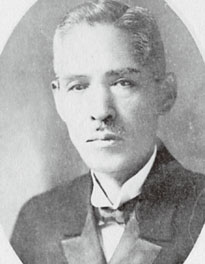
大隈栄一 『中京名鑑 昭和7年版』
創業者は大隈栄一という。元は佐賀県の巡査だった。
裸一貫で創業した大隈栄一は、長年逆境と闘ったが、明るい光が差し始めた。それは第一次世界大戦勃発により、経済界に好況が訪れたことにほかならない。既に日露戦争以来、工作機械の製造に手を染めていた栄一は、東京砲兵工廠から、小銃用旋盤と工具製造機の注文を受けた。
大正3年(1914)には大隈式自動歯切旋盤により特許を取得して、本格的な工作機械メーカーの道を歩み始めた。翌年には陸軍砲兵工廠からの注文を受けて、各種兵器製造機械を納入、5年10月には同工廠の特命を受けて12月より?薬装弾機の製作を開始するなど、次々と新製品を製作し、その技術力を高めていった。5年に社名を大隈鐵工所と改称、7年7月に資本金100万円(職工数270人)の株式組織に改組した。
栄一の周囲には、幾人かの熱烈な支援者が現れた。資金の面倒をみて、大量生産に応じうる工場設備の拡張を助けた愛知銀行頭取の渡邉義郎は、その一人である。また、岡谷合資会社の岡谷惣助も、全面的に支援した。
〔参考文献『名古屋商人史話』〕
発刊に寄せて
序文
大正元年(1912)
大正2年(1913)
大正3年(1914)
大正4年(1915)
大正5年(1916)
吉野作造が名古屋で民本主義を説く
- その頃、日本は 好景気で狂乱物価
- その頃、名古屋は 大戦のおかげで重工業が勃興
- その頃、日本は 工場法が施行され不十分ながら労働者保護へ
- <この年に誕生した会社>
ピンチを一致団結して乗り切る
クサカ - <この年に誕生した会社>
「もったない」精神をビジネスに エス・エヌ・テー - <この年に誕生した会社>
ロングセラーの「あべっ子ラムネ」 安部製菓 - <この年に誕生した会社>
「土木は世の中を良くする仕事」の信念を貫く 朝日工業 - <この年に誕生した会社>
自己変革に挑む地場の繊維産業
茶久染色 - <この年に誕生した会社>
「長生き健康法」で企業を永続
妙香園
大正6年(1917)
大正7年(1918)
大正8年(1919)
大正9年(1920)
大正10年(1921)
大正11年(1922)
大正12年(1923)
大正13年(1924)
大正14年(1925)
大正15年(1926)
昭和2年(1927)
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274