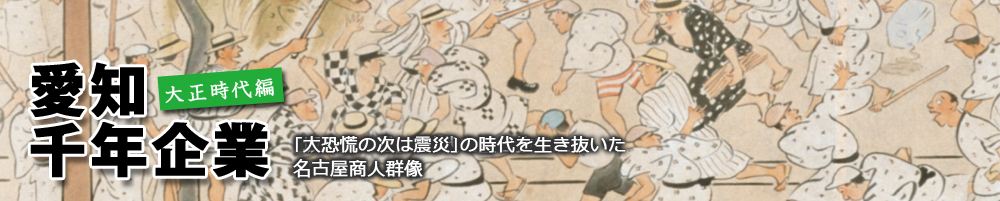
大正10年(1921)チャップリンのサイレント映画『キッド』が大ヒット
その頃、名古屋は…不況で繊維企業の淘汰が進む
大戦後、名古屋は大阪に次ぐ全国第2位の紡績都市に躍り出た。だが、その繊維産業は大正9年(1920)の恐慌で打撃を受けた。
名古屋市内の繊維工業の生産額は、前年8年の9千100万円から6千800万円へと減少し、全生産額に占める比率も46%から41%へと低下した。繊維工業は、製造軒数も急減した。大正8年の7千300戸からほぼ一貫して減少し、昭和3年(1928)には1千500戸へと急減した。零細工場が急速に淘汰された。
このように打撃を被った繊維工業だが、それで衰退したわけではなかった。大戦後の反動恐慌の後でも、名古屋の工業生産額の50%以上を占めた。その中でも、60%以上を占めたのが、綿糸紡績と綿織物であった。とりわけ紡績業は、大戦後半期から次々と大規模工場が名古屋に設置され、大戦後の発展の基礎を形づくった。大戦後にも設立・進出は続き、帝国撚糸織物の綿糸紡績進出、内外紡、日清紡と続いた。
また、繊維産業に続いて生産額の高さを保持した化学工業は、窯業とマッチ製造であった。陶磁器業は我が国の一大中心地たる地位を占め続けた。
大正8年に設立された日本碍子(現・日本ガイシ)は、昭和2年に隧道式窯の築造を計画し、翌年アメリカ・ハロップ社が使用していた直火式隧道窯を自社で完成させ、日本製品の欠点であった質の不均一性を克服した。
その頃、名古屋は…三菱電機名古屋製作所が設立
「慢性不況」の時代ではあったが、名古屋では必ずしも不況一色には塗りつぶせない変化が生じていた。企業倒産は毎年100件を下回ることはなかったが、新設件数は、一貫してそれを上回り、会社総数は増え続けた。
不況知らずの進展を遂げていたのが、機械器具工業であった。生産額の上位を占めたのは、大正14年(1925)で見ると、車両534万円(鉄道車両197万円、電鉄車両179万円、機関車58万円)、時計271万円、力織機262万円、ポンプ127万円、自転車100万円の順であり、いずれも大戦前ないし大戦中に発展した分野であった。しかし、大戦後には大戦期後半に始まった新たな動きが本格化した。それが自動織機と、紡績機それに航空機の生産であり、大戦後の急速な電化に伴う電気機械器具であった。
電気機械器具の生産にとって、重要な意味をもったのが、大正10年1月の三菱電機株式会社(13年9月に三菱電機名古屋製作所となる)の設立であった。同社は小型電動機と電熱器の大量生産を開始している。三菱が名古屋に製作所を設置したのは、電力が豊富だったからである。
また、三菱内燃機製造株式会社(現・名古屋航空宇宙システム製作所)名古屋工場が完成し、本格的発動機生産の基礎を固めた。〔参考文献『新修名古屋市史』〕
その頃、名古屋は…隣接町村を合併して市域を拡大
名古屋市は大正10年(1921)、隣接16町村を合併した。9月、鶴舞公園において、「隣接町村併合祝賀会」を催した。
市域の拡大とともに、周辺への工場進出の激増、人口の増加、従業員等の住宅地の増加があり、その結果として耕地整理、区画整理が必要とされるに至った。
工場進出が相次いだのは、呼続町近辺であった。その一つの大きな要因は、日露戦争時の明治37年(1904)に愛知郡熱田東町に東京砲兵工廠熱田兵器製造所が設立され、さらに大正6年には隣接する高蔵の地に大阪砲兵工廠名古屋兵器製造所が設けられたことにある。その関連で協力工場が出来上がった。
発刊に寄せて
序文
大正元年(1912)
大正2年(1913)
大正3年(1914)
大正4年(1915)
大正5年(1916)
大正6年(1917)
大正7年(1918)
大正8年(1919)
大正9年(1920)
大正10年(1921)
チャップリンのサイレント映画
『キッド』が大ヒット
- その頃、世界は ドイツでベルサイユ体制打倒を叫ぶ過激派が台頭
- その頃、日本は 原首相、凶刃に倒れる
- その頃、名古屋は 不況で繊維企業の淘汰が進む
- その頃、名古屋は 上遠野富之助が名古屋商業会議所の会頭に就任
- その頃、豊田は 上海工場を法人化して株式会社豊田紡織廠とする
- <この年に誕生した会社>
軍靴の靴底金具から靴のトップブランドに発展 マドラス - <この年に誕生した会社>
堅実な夫と節約家の妻で会社を盛りたてる 深田電機 - <この年に誕生した会社>
ガラス製のコースターのメーカーとして始まった タケダ - <この年に誕生した会社>
木材の防腐技術を生かして発展
大日本木材防腐
大正11年(1922)
大正12年(1923)
大正13年(1924)
大正14年(1925)
大正15年(1926)
昭和2年(1927)
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274