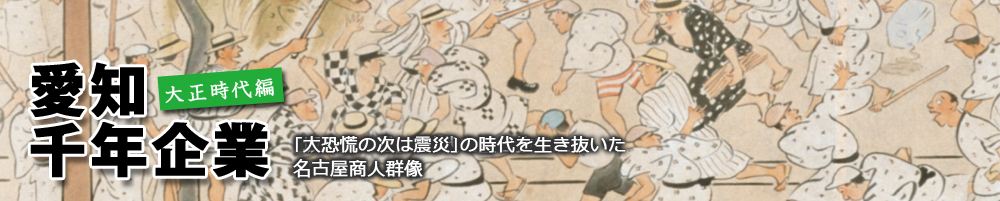
大正3年(1914)暗殺事件を契機に第一次世界大戦が勃発
その頃豊田は…紡績工場を併設して工場名を「豊田自動紡織工場」に改称

佐吉が成功した暁に建てた邸宅。東区の現・ダイキン工業の場所
にあった 『豊田佐吉傳』
豊田佐吉のつくった豊田自動織布工場は大正3年(1914)、紡績工場を併設した。これを機に「豊田自動紡織工場」に改称した。
佐吉が紡績工場までつくった理由は、やはり自動織機の開発にあった。糸が切れて織機が停止した場合に、その原因が糸にあるのか、機械にあるのかを特定する必要があった。そのためには、高品質な糸を自ら作り上げる必要があった。
また、長男喜一郎は大正3年9月、仙台の旧制第二高等学校の工科に入学した。喜一郎が最も興味を持ったものは製図だった。特に機械や部品の設計と製図は、二高時代から以後は得意というばかりか、むしろ彼の生活の一部となっていた。そして、それは終生変わることがなかった。
<どえらい人物〉豊田佐吉の人生最初の支援者・石川藤八が逝去

石川藤八
『豊田佐吉とトヨタ源流の男たち』
大正3年(1914)は、豊田佐吉にとって悲しい出来事から始まった年であった。1月19日、支援者の石川藤八が亡くなった。享年51という若さであった。
故郷では変人扱いされてきた佐吉だが、藤八は、その佐吉の才能や意欲を見いだし、応援した最初の人物だった。
藤八と佐吉の出会いが、いつ、どこでだったのか正確なことは定かではないが、筆者は詳細な年表を作って、その足跡を追ってきた。それは明治27年(1894)のことだったと想像する。
資金面で常に苦労してきた佐吉が、藤八の支援を求めて、半田乙川を訪問したようだ。石川家は、半田乙川の庄屋だった。庄屋として米を扱いながら、塩や海産物や綿織物まで売る商家でもあった。藤八を代々襲名していて、地元では敬意を込めて「藤八さん」と呼ばれていた。石川家は、本宅と別宅を合わせて1千坪を超える屋敷を所有していた。大きな蔵のある屋敷に住み、100人を超える使用人を抱えていた。
その7代目藤八が、佐吉の人生最初の支援者になってくれた。7代目藤八は、元治元年(1864)の生まれだから、出会った時は佐吉が27歳、藤八が30歳だったことになる。
佐吉の意気込みを知った藤八は、賭けてみることにした。そして、石川家の2階に発明に専念できるように部屋を与えた。試験工場まで建てた。
佐吉は石川家で発明に没頭した。弟平吉や弟子の豊田利喜松も呼んだ。この恵まれた環境の下で発明は順調に進み、ついに明治28年秋に力織機の試運転に成功した。佐吉はこの石川家で、明治30年初めまで3年近くを過ごすことになった。
力織機という画期的な発明が完成したので、それを使って綿布を作る事業を興すことになった。藤八と佐吉は、明治30年秋に乙川綿布合資会社を設立した。資本金は6千円だった。藤八が資金と土地を提供し、佐吉が織機を提供しての発足だった。
工場は、翌31年に完成し、国産初の動力織機を運転する織布工場が操業開始した。60台もの豊田式木鉄混製力織機がずらりと並んでいた。機械が大量の綿布を作り出すというのは、まさに革命的だった。
この乙川で作られた綿布は、織りムラがなく、とても人手ではできない代物だった。その品質の良さが三井物産の目にとまり、一躍脚光を浴びることとなる。
佐吉は、この乙川綿布合資会社が順調に発展し始めたのを見届け、自分の持ち株を藤八に譲り、乙川綿布会社から手を引いた。そして名古屋の武平町にできていた工場での織機製作と、織布に専念するようにした。そこで生み出された織機は、全国を席巻することになる。
2人の関係は、当初こそ支援する側とされる側ということで始まったが、互いに認め合うようになり、無二の親友になり、良き相談相手になっていった。
佐吉は事業で成功してからも、この藤八から受けた恩義を忘れなかった。石川家に来る時は、半田駅から人力車に乗って乙川に来るが、乙川に入ると人力車を降りて歩いたという。恩人藤八の家の前に乗り付けるようなことはしなかった。
その藤八が大正3年に亡くなった。佐吉は、妻浅子と共に葬儀に参列した。そして一周忌、三回忌、七回忌にも参列した。当時の佐吉の家は名古屋だったが、交通事情が不便だったので乙川まで行くのは前泊が必要だった。佐吉はそれでも参列を欠かさなかった。佐吉は既に大成功者になっていたが、昔の恩義は忘れない人間だった。〔参考文献『豊田佐吉とトヨタ源流の男たち』〕
★ 佐吉のエピソード 佐吉が盟友と飲み明かした料亭「花月」
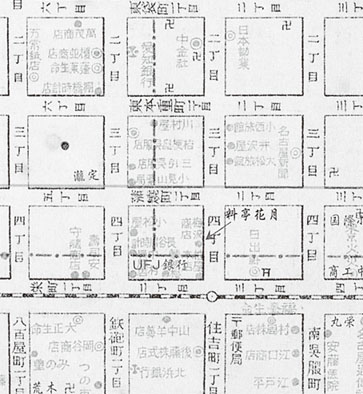
料亭「花月」は中区錦3丁目21番地で、現・三菱東京UFJ
銀行名古屋ビルのブロックの東側にあった。現在は駐車
場になっている
豊田佐吉は酒が好きで、よく飲んだ。名古屋へ出る前後には、豊橋の森米治郎、宅間喜右衛門、二川の鈴木正次郎、伊藤久八などが飲み仲間だった。佐吉は1升飲んでも2升飲んでも形を崩さず、しっかりした飲みっぷりであった。
明治27年(1894)、豊橋で糸繰返機の発明をした佐吉は、その販売のため、また懸案の動力織機を研究すべく名古屋市の朝日町で創業した。ここで彼が知り合ったのが、服部兼三郎であった。兼三郎は佐吉の機械を大量に購入するようになり、資金援助をするようになった。
名古屋富澤町の「花月」が常宿であった。いつも佐吉が主唱者で、発明上の名案を得たとか、一つの発明を仕上げた時、佐吉は欣喜雀躍して、石川藤八・服部両氏を花月へ招集した。そして、3人寄れば2日でも3日でも徹底的に飲んだという。
服部兼三郎との友情は、乙川綿布合資会社の石川藤八を交え、世間から三幅対(さんぷくつい。三つで一組になるもの)と称揚されるほどであった。後年、共に名を成した3人が悠揚と杯を交わす姿がしばしば見られた。
だが、公の席では佐吉は1滴も飲まなかった。部下を招いて祝宴を張った時も、自分は特製の酒(茶)を飲んでいた。上海では六三園でよく飲んだ。そして、佐吉一流の支那論を述べ立てた。
発刊に寄せて
序文
大正元年(1912)
大正2年(1913)
大正3年(1914)
暗殺事件を契機に第一次世界大戦が勃発
- その頃、名古屋は 戦争の影響を悲観して不景気風
- その頃、名古屋は 福澤桃介が返り咲き、名古屋電燈の社長に
- <どえらい人物>木曽川でダムを造り電力王になった福澤桃介
- その頃、豊田は 紡績工場を併設して工場名を「豊田自動紡織工場」に改称
- <この年に誕生した会社>
伊勢湾台風で利他の心を実践
お漬物の丸越 - <この年に誕生した会社>
大須がルーツの家具のメガストア 安井家具
大正4年(1915)
大正5年(1916)
大正6年(1917)
大正7年(1918)
大正8年(1919)
大正9年(1920)
大正10年(1921)
大正11年(1922)
大正12年(1923)
大正13年(1924)
大正14年(1925)
大正15年(1926)
昭和2年(1927)
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274