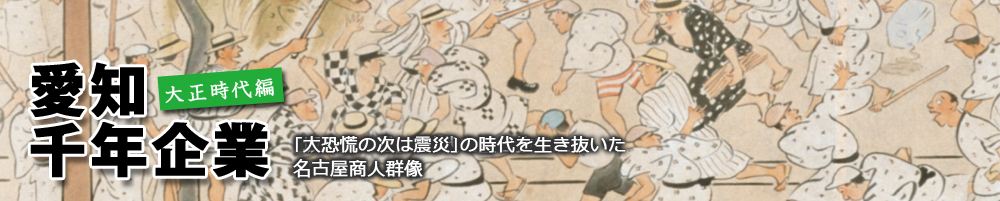
この年に誕生した会社
伊勢湾台風で利他の心を実践
お漬物の丸越
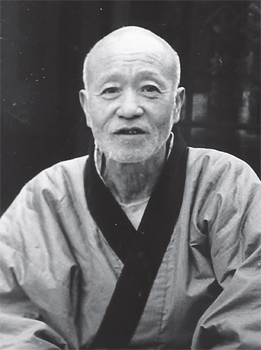
野田市次郎
漬物の「小夜子」で知られる丸越は、大正3年(1914)の創業だ。
丸越は、野田市次郎が創業した。市次郎は明治15年(1882)に生まれた。父は栄三郎で、母はあいだった。父は接骨院を営んでいた。市次郎は6人兄弟の三男だった。市次郎は学校を卒業後に、熱田区高蔵で表具師を開業した。この表具師の仕事は、数人の職人を抱えるまでに発展したが、職人を兵役で取られてしまったこともあり廃業した。
表具師の仕事を辞めた市次郎は、親類の勧めもあり、次に漬物製造販売という新分野に挑戦した。野田屋本店という屋号で大正3年に南区内田橋(現・豊田本町の交差点の北東側)に店を開き、たくあんなどを作った。32歳の時だった。
だが、日本は昭和に入り、戦争の足音が聞こえてくる。そして昭和20年(1945)の敗戦へ。野田屋は空襲で店舗や住居を全焼した。
戦後、運が良かったのは、3人の息子が会社に入ってくれたことだ。長男の一次は明治40年生まれで、昭和20年の時は38歳だった。そして兵役に行っていた次男二郎、三男三郎が復員して戻ってきた。
3兄弟は、一致団結して家業の再建に乗り出した。野田屋は昭和21年、内田橋でバラックを建てて、漬物の製造を再開した。また、東海市の名和にも工場を建てた。
野田屋は、昭和25年に株式会社丸越になった。社長には一次が就任した。二郎は専務になり製造を、三郎は常務になり営業を担当した。
新生丸越が戦後に始めたのは、高級な奈良漬などの製造だった。当時は戦後のドサクサで、そんな高級品が売れるのかと危ぶむ向きもあったが、あくまでも味にこだわる路線は当たり、固定客を作った。
味にこだわる丸越の路線は注目されるところとなり、昭和29年に名鉄百貨店が開業するとともに食品売り場で店を開くことができた。これが戦後の発展の基礎になった。
創業者市次郎は、子供たちの成功を見届けたうえで、昭和32年に亡くなった。76歳だった。
そこに、伊勢湾台風が丸越を襲い、内田橋の工場が壊滅した。取引先の間では、もはや再建できないのでは?と危ぶむ向きもあったようだ。
丸越は、ピンチに陥った。だが、そこで一次が打ち出したのは、取引先の救済だった。売り先には小売店がたくさんあったが、被災した店に対して、「お金ができてからの支払いで結構です」と知らせた。「被災して苦しんでいるのはお互いさま」という気持ちからだった。
この丸越の方針は、中央市場では評判になった。相手本意の姿勢に、取引先が感銘を受けた。「丸越さんに恩返しをしたい」という取引先が増え、自分の方から大八車を引いて商品を買いに来てくれるところもあった。取引銀行の東海銀行内田橋支店も積極融資に乗り出した。
周囲の支援のたまもの―。丸越は昭和34年の年末には、より高台の瑞穂区玉水町で工場を賃借して移転することができた。まさに災い転じて福となった。
丸越は、スーパーの台頭という流通革命の波にも乗ることができた。昭和43年にはユニーが昭和区桜山に出店したが、丸越はそこに漬物の専門店をつくった。その店の経営も、既存取引先だった小売店とFC契約を結んで入ってもらい、三方良しを実現した。
昭和59年には、一次の長男幸男が社長になり、3代目の時代に入った。幸男は昭和63年、浅漬「小夜子」を売り出した。当時の漬物業界では、ブランドというのはまだ珍しかった。テレビCMなどで1億円以上を投資して、知名度を高めた。これが成功して、売上高は急増した。
現社長は野田明孝氏で、幸男の長男だ。会社の規模は、漬物業界で指折りだ。漬物は年々消費量が減り厳しい環境だが、明孝社長は「創業の原点に戻り、おいしさを追求する」と言い切る。〝日持ちする、お漬け物風サラダ〟という新しい商品の開拓に励み、漬物の日本一を決める「T‐1グランプリ」では、平成24年(2012)に「ごぼうとナッツの胡麻味噌漬」が1位に輝いた。
本社所在地は、名古屋市天白区道明町71である。
発刊に寄せて
序文
大正元年(1912)
大正2年(1913)
大正3年(1914)
暗殺事件を契機に第一次世界大戦が勃発
- その頃、名古屋は 戦争の影響を悲観して不景気風
- その頃、名古屋は 福澤桃介が返り咲き、名古屋電燈の社長に
- <どえらい人物>木曽川でダムを造り電力王になった福澤桃介
- その頃、豊田は 紡績工場を併設して工場名を「豊田自動紡織工場」に改称
- <この年に誕生した会社>
伊勢湾台風で利他の心を実践
お漬物の丸越 - <この年に誕生した会社>
大須がルーツの家具のメガストア 安井家具
大正4年(1915)
大正5年(1916)
大正6年(1917)
大正7年(1918)
大正8年(1919)
大正9年(1920)
大正10年(1921)
大正11年(1922)
大正12年(1923)
大正13年(1924)
大正14年(1925)
大正15年(1926)
昭和2年(1927)
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274