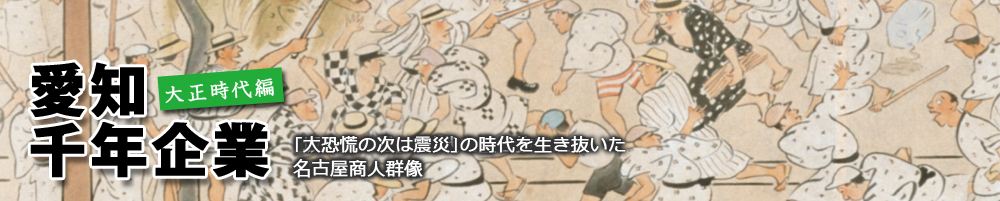
大正9年(1920)戦後恐慌に突入
その頃、豊田は…上海工場が完成
豊田佐吉は大正9年(1920)、上海において工場を完成させた。工場には最新式の織機を導入して、稼働を始めた。工場敷地は9つの区画に分類し、そこに紡績工場、織布工場を並べた。周囲をすべてれんがで囲み、屋根はのこぎり型でスチールを敷いた。

上海における邸宅 『豊田佐吉傳』
日本では質素に暮らしていた佐吉だが、上海では大きな邸宅を構えた。フランス租界地で5千坪の大豪邸を購入した。個人の家というより、城のような威容を誇る大邸宅であった。広い敷地はテニスコートが数面つくれるほどの庭があって、全体に芝生が張られていた。住居空間も大きく、地下1階、地上3階の建物であった。1・2階に佐吉一家が住み、3階には社員などが寄宿していた。
息子の喜一郎は大正9年、工学部最終年として卒業論文の作成に取りかかった。テーマは、工場の原動機に関する研究であった。「上海紡績工場原動所設計書」という表題だった。
工学部卒業後、佐吉の意向もあり、喜一郎は大正9年9月から10年3月まで、東京帝国大学法学部で学んだ。その後地元の名古屋に戻った喜一郎は、豊田紡織に入社した。
その頃、名古屋は…三菱内燃機製造株式会社が設立
大正9年(1920)5月に設立された三菱内燃機製造株式会社名古屋工場(現・三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所)(10年三菱内燃機名古屋工場と改称、さらに昭和3年〈1928〉には三菱航空機名古屋工場と改称)が、10年5月から生産を開始し、翌年から航空機生産に特化した。
陸海軍からの注文を受け、大量生産を実施し、戦闘機、偵察機、攻撃機、爆撃機、練習機などを生産していった。こうした航空機産業が名古屋で発展した背景には次の理由があった。
機体原料の木材集散地であったこと、電力が豊富なこと、製作機試乗に好都合な濃尾平野があること、水上飛行機試乗に好都合な伊勢湾があること、などであった。こうした航空機生産を支えたのが、浅野木工場のベニヤ板、岡本自転車の車輪、大同電気製鋼所(現・大同特殊鋼)の特殊鋼であった。
こうして名機・ゼロ戦が誕生する土壌が名古屋で芽生えるようになった。ゼロ戦は愛知県内で製造されることとなり、中部地方が航空機産業のメッカとなる。
〔参考文献『明治大正図誌第9巻 東海道』〕
発刊に寄せて
序文
大正元年(1912)
大正2年(1913)
大正3年(1914)
大正4年(1915)
大正5年(1916)
大正6年(1917)
大正7年(1918)
大正8年(1919)
大正9年(1920)
戦後恐慌に突入
- その頃、世界は 国際連盟が発足。日本が常任理事国へ
- その頃、名古屋は 堅実経営で恐慌を乗り切った3大銀行
- その頃、名古屋は 大安売りを実施して市民の喝采を浴びた、いとう呉服店
- その頃、名古屋は 一代の風雲児・服部兼三郎が商売に失敗して自殺
- 服部商店を再建して興和の基礎を築いた三輪常次郎
- その頃、豊田は 上海工場が完成
- <この年に誕生した会社>
〝身の丈に合った経営〟に徹する住宅総合商社 丸美産業 - <この年に誕生した会社>
工業用酸素の草分け 江場酸素工業
大正10年(1921)
大正11年(1922)
大正12年(1923)
大正13年(1924)
大正14年(1925)
大正15年(1926)
昭和2年(1927)
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274