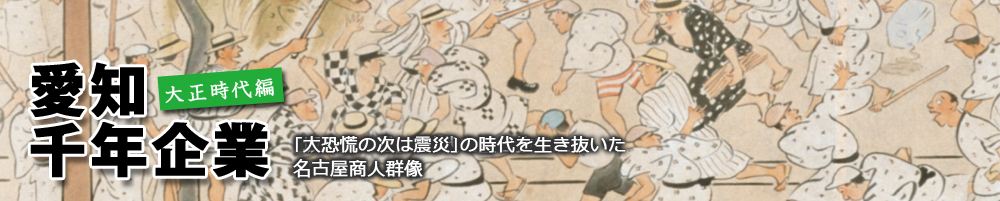
この年に誕生した会社
ガラス業界の再編を乗り越えて発展
宮吉硝子
大正15年(1926)、若宮八幡社の西側で「宮吉(みやきち)硝子」は創業した。創業者の立木(ついき)吉次郎は、明治34年(1901)生まれで、大垣の農家の出身で7男だった。大阪の「宮惣硝子」に奉公に上がり、その一文字をもらって名古屋で創業した。当時、日本ではガラス産業は勃興期だったが、幸運にも旭硝子の代理店になれた。創業の場所は、名古屋市中区末広町(本町通で広小路の南側近辺)である。
2代目の亨は、昭和6年(1931)の生まれで、24年に家業に入った。同時に慶應義塾大学に入学し、学業もそこそこに家業に励んだ。戦後間もなくの頃は、配給制であり、モノの仕入れが困難だった。そこで付加価値を拡大するため、ガラスの加工業に乗り出した。ガラスの加工業とは、鏡の製造販売のことだった。単なる鏡販売では妙味が薄いので、風呂屋の鏡に焦点を絞った。風呂屋の鏡には広告を入れるので、定期的に買い直すからだ。屋号も「宮吉カガミ店」に変えてPRに努めた。
昭和30年代になると、百貨店のショーケース用にガラスの需要が高まり、店装業界を開拓した。吉次郎は昭和39年に死去した。同時に亨が社長に就任した。
亨は、社員教育に熱心だった。商いとはどうするべきものか、実践的に教え込んだ。通常なら任せない仕入れまで担当させた。そして給与制度の充実も図った。商店は戦後になっても、住み込みの丁稚は大した給与も支払われない時代が続いていたが、昇給や賞与支給を行い長年勤務できるようにした。
3代目の社長として登場するのは、亨の長男の彰一氏だ。彰一氏は昭和34年生まれで、平成4年(1992)に社長になった。その後間もなくして、平成6年に日米構造協議があり、日本の板ガラス業界に大きなメスが入った。それまで割高だった日本の板ガラスの価格が下落した。おまけに建築不況で板ガラスの需要が減り、単価減×数量減というダブルパンチをくらった。売上高の7割を占める板ガラスが、3分の1にまで落ち込んだ。
亨が平成11年に亡くなったので、その後の経営は彰一氏に任された。ここからが彰一氏の正念場だった。コンビニなど全国の小売業チェーンを相手に、全国ネットで24時間対応できる体制を整えた。また、ガラスの切断はそれまでメーカーや問屋の仕事だったが、自社での切断や施工を止めて、それを小売店に任せるように切り替えた。小売店で勤務する職人をとことん大事にする形で、協業関係を築いた。おかげで現在では、工事施工の売上高は業界でもトップクラスを誇るまでになっている。ガラスの問屋の軒数はピーク時と比べて半分以下になったが、同社は逆に発展を遂げ、日本で指折りの存在になった。
彰一社長は、「ガラスの切断・施工を行う職人さんは私にとって救世主だった。職人さんを大事にして、存在価値のある会社にしていきたい。先代は『価値の創造』という社是を残してくれたので、私も存在価値のある会社を目指す」と抱負を語っている。
本社所在地は、名古屋市昭和区福江3‐7‐2である。
発刊に寄せて
序文
大正元年(1912)
大正2年(1913)
大正3年(1914)
大正4年(1915)
大正5年(1916)
大正6年(1917)
大正7年(1918)
大正8年(1919)
大正9年(1920)
大正10年(1921)
大正11年(1922)
大正12年(1923)
大正13年(1924)
大正14年(1925)
大正15年(1926)
大正天皇が崩御
- その頃、名古屋は 佐吉が豊田自動織機製作所を設立
- 地域振興と家業の発展にまい進
岡谷惣助清治郎 - <この年に誕生した会社>
地元資本が大同合併して誕生
東陽倉庫 - <この年に誕生した会社>
時計商からアパレルへ。時流に沿う事業展開 リオグループ - <この年に誕生した会社>
「金の鳥を目指して翔ぶ銀の鳥」の思いを込めて 銀鳥産業 - <この年に誕生した会社>
ガラス業界の再編を乗り越えて発展 宮吉硝子
昭和2年(1927)
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274