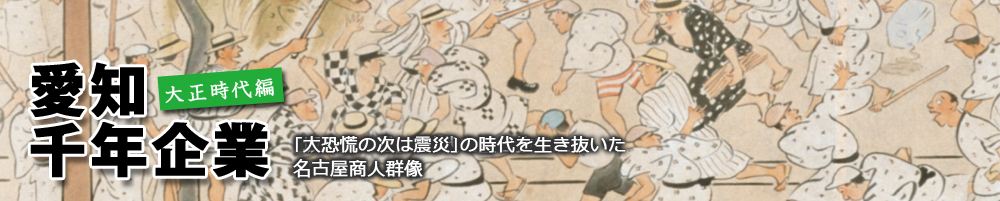
この年に誕生した会社
ニッチな分野で独自の技術力を発揮
湯浅糸道工業

糸道という商品の可能性に着目した
湯浅四郎
「糸道(いとみち)」と言われてもピンとくる向きは少ないだろうが、繊維機械の部品である。糸を紡ぐ繊維機械には糸が通る箇所がたくさんあるが、そこには「糸道」と呼ばれる部品が使われている。その糸道の専業メーカーが湯浅糸道工業だ。
同社は大正13年(1924)8月、湯浅四郎が創業した。四郎は明治32年(1899)に茨城県で生まれた。商業学校を卒業して横浜で問屋に就職し、製糸工場で使用する資材を販売した。だが、関東大震災で被災して店が廃業したため、やむなく独立を決意した。
四郎は、湯浅商店という店を名古屋市の東区白壁近辺で創業した。問屋として、製糸・撚糸・紡織機用各種糸道、レーヨン・メリヤス用各種糸道など、繊維工場で必要になるものを幅広く扱った。場所はその後、菊井町、天神山へと移ったが、その天神山は土地を購入して数人の使用人を擁するまでになった。
だが、戦争になり、空襲を受け、全焼してしまった。不幸中の幸いだったのは、家族の中から戦争の被害者が出なかったことだ。戦後、すぐに営業を再開した。繊維産業は戦後急速に発展したので、同社も順調に回復できた。
戦後は、世代が交替して、子供たちが活躍するようになる。四郎には5人の男子がいたが、みな家業に入った。四郎は長男の彪たちを信用して任せるようになった。長男の彪を筆頭に5人の男兄弟は、製造業への転換を目指した。昭和38年(1963)に湯浅糸道工業株式会社を設立して、名古屋市天白区に工場(現・本社)を建設し、硬質クロムめっき加工糸道を製造し始めた。
同社が発展できた最大の要因は、家族の仲の良さだった。5人の男兄弟は性格が異なり、持ち味が違っていた。ある者は営業を、ある者は技術を、ある者は海外営業を役割分担した。
最大のピンチだったのは、昭和48年の第一次オイルショックだった。合成繊維の原料である原油が高騰し、業界は大ピンチに陥った。だが、兄弟は一致団結して乗り切った。
繊維機械というと、今どきは衰退産業のようなイメージがあるかもしれない。事実、糸道の市場は世界でも100億円未満しかないという。日本にはかつて糸道のメーカーが多数あったが、どんどん姿を消してしまった。そんな中で同社は今なお糸道専業メーカーとして、業績を堅実に伸ばしている。繊維機械が使われるのは発展途上国であるため、海外市場の開拓に力を入れてきた。
現在の社長は、四郎の三男である宏の長男の伸一郎氏だ。今日まで残ってきた要因として、「規模を追わず、身の丈に合った経営に徹したこと」を挙げる。「繊維の品質は糸道によって左右されるので、糸道は独自の技術力を発揮できる分野だった。糸道というニッチな分野から出なかったことが幸いした」と語っている。
創業者の四郎は、平成6年(1994)に95歳で天寿を全うした。その教えは「他人のふんどしで相撲を取るな。いくら好調な時でも自己資金の範囲内とせよ。支払い手形を出すな。借入金はしない」というものだったが、今でも守られている。
本社所在地は、名古屋市天白区元八事1‐47である。
発刊に寄せて
序文
大正元年(1912)
大正2年(1913)
大正3年(1914)
大正4年(1915)
大正5年(1916)
大正6年(1917)
大正7年(1918)
大正8年(1919)
大正9年(1920)
大正10年(1921)
大正11年(1922)
大正12年(1923)
大正13年(1924)
宮沢賢治が詩集『春と修羅』、童話『注文の多い料理店』を出版
- その頃、世界は アメリカが新「排日」移民法を制定
- その頃、日本は 愛知出身の加藤高明が首相に就任
- その頃、名古屋は 福澤桃介が見栄とはったりで外資調達に成功
- その頃、名古屋は 九日会が財界を牛耳る
- その頃、世界は 上海で5・30
事件発生、中国人デモ隊にイギリス人警官隊が発砲 - <この年に誕生した会社>
ニッチな分野で独自の技術力を発揮 湯浅糸道工業 - <この年に誕生した会社>
角ナットの納入に始まるトヨタとの信頼関係 メイドー
大正14年(1925)
大正15年(1926)
昭和2年(1927)
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274