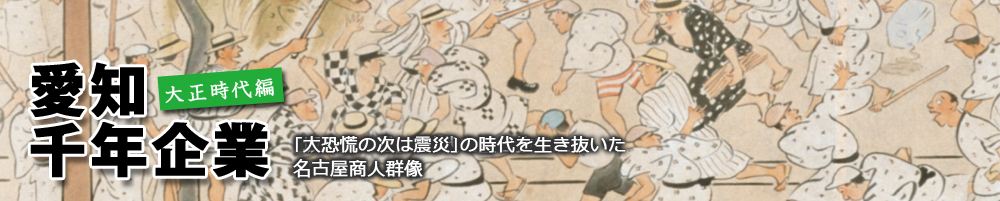
大正4年(1915)芥川龍之介が処女作『羅生門』を発表
その頃、名古屋は…織物と陶磁器が1位を競う
大正4年(1915)は、名古屋の経済界が空前の好景気に沸いた。特に綿織物の活況は著しく、輸出向けの綿布を中心に生産量も飛躍的な伸びを示した。
第一次世界大戦が勃発すると、大正4年から名古屋産品の輸出は勢いを増し、とりわけ6年以降の急増ぶりは目を見張らせた。

織物の輸出額は、明治43年(1910)には33万円で5位だったが、大正2年に64万円、大正5年に419万円となり、6年には1千万円を超え、陶磁器を凌駕して輸出品のトップに立った。さらに7年には前年の倍の2千万円と激増した。
陶磁器は、明治43年には277万円で1位、大正5年まで一貫してトップの座にあった。6、7年には織物に抜かれたものの、7年には大正3年の5倍近い1千万円を超える急増ぶりを示した。輸出向けの飲食器は、スープ皿・コーヒー碗・肉皿・パン皿・ミルク入れ・紅茶入れ・砂糖入れなどであった。
オカイコサマと呼ばれていた生糸も急伸した。生糸は、明治30年代後半から大正にかけて、全国的には生糸輸出の好調による繭価格の上昇に引かれて、養蚕が農家の有力な収入源として急速に普及していくのであるが、愛知県もその例外ではなかった。明治35年から44年までに産繭量・価額共に約3・2倍に、44年から大正8年までに産繭量では1・6倍、価額では4・6倍に急伸している。
〔参考文献『新修名古屋市史』〕
その頃、名古屋は…鶴舞公園で即位を祝う御大礼奉祝会祝賀式
大正4年(1915)の11月10日、京都では大正天皇の即位の大礼が京都御所紫宸殿で挙行された。
天皇は、大礼のため京都へ向かう途中で、名古屋離宮に駐泊した。小学校児童および中等学校生徒の提灯行列が催され、煙火を打ち上げてお迎えした。
その日は、名古屋でも御大礼奉祝会祝賀式が開かれた。鶴舞公園において、松坂屋のルーツであるいとう呉服店の少年音楽隊の奏楽があり、祝盃を挙げて両陛下万歳を三唱した。各学校では遙拝式を挙行、折から陸軍の礼砲、各会社の汽笛が一斉に秋空に響き、夜は提灯行列を行い国を挙げての盛大な佳日となった。
同日、伊藤次郎左衛門が従五位、神野金之助・鈴木摠兵衛・岡谷惣助・滝兵右衛門が従六位に叙せられた。
大正天皇は、翌年頃から健康がすぐれず、政務を十分に執ることができなくなり、皇太子裕仁が摂政に任じられることになる。
発刊に寄せて
序文
大正元年(1912)
大正2年(1913)
大正3年(1914)
大正4年(1915)
芥川龍之介が処女作『羅生門』を
発表
- その頃、世界は 第一次世界大戦で毒ガスなど大量殺戮兵器が使用される
- その頃、日本は 大戦景気が始まる
- その頃、名古屋は 織物と陶磁器が1位を競う
- 婿入りして豊田グループの総帥になった豊田利三郎
- <この年に誕生した会社>
バナナにこだわったフルーツ提案企業 名古屋バナナ加工
大正5年(1916)
大正6年(1917)
大正7年(1918)
大正8年(1919)
大正9年(1920)
大正10年(1921)
大正11年(1922)
大正12年(1923)
大正13年(1924)
大正14年(1925)
大正15年(1926)
昭和2年(1927)
Copyright(c) 2013 (株)北見式賃金研究所/社会保険労務士法人北見事務所 All Rights Reserved
〒452-0805 愛知県名古屋市西区市場木町478番地
TEL 052-505-6237 FAX 052-505-6274